
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』
シリーズ刊行10周年記念企画
エピソード無料公開 第8弾
公開期間:8月22日~9月26日
その自動手記人形の休日は静けさの中で終わる。
夏の終わりの過ごし方は大抵決まっている。朝方はまだ庭の木々を窓辺から眺め、昼を過ぎると日傘をさして邸宅の周りを散策する。斜陽にすべてが包まれるまで木陰で本を読み、夜は次の旅支度をしている。
人が見ていないところでは銃の分解と組立を行い、腕が鈍らないように木々から落ちゆく葉にナイフを投げたりしているが基本的には、そう。
基本的には穏やかさに包まれている。彼女を子どものように扱う義父母の影響の賜物だろう。
そもそも彼女の静寂をわざわざ破りに行こうという者は少ない。
気後れという感情を、人に与えがちな存在なのだ。
寡黙で、冷たい美しさの持ち主。とりまく時や人も自然と息すら潜めてしまう。
「ヴァイオレット。あんた、あたしと一緒にくるのよ」
遊びに誘うには向かない相手だ。
「飛行手紙と自動手記人形 前編」
ライデンシャフトリヒ、首都ライデン。
街の本通りから外れた小路。小さな商店が立ち並ぶその通りに一つだけ顔を突き出して君臨している建物がある。C・H郵便社という郵便業界新規参入の若い会社だ。
風見鶏を掲げた薄緑色のドーム型の屋根を持つ尖塔がこの郵便社の目印と言えるだろう。
尖塔を囲むように深緑の屋根が続き外壁は味のある色合いに日焼けた赤煉瓦で出来ている。
アーチ型の玄関には鉄板に金の字で印された店名が。
扉を開けると陽気な音のベルが鳴り響き客の来訪を告げる。
中は入るとすぐにカウンターがありそこで郵便物の受付をしてくれる仕様だ。
建物は三階建てで一階は郵便受付、二階は事務所、三階の尖塔は社長の住宅になっていた。
いま現在二階の事務所では内勤業務の者達が時間と戦いながら必死に業務をこなしていた。
彼らの会社では『締め日』と呼ばれる日が存在していた。
ひと月の間の各種取引、それにまつわる報告書、請求書、支払い証明、会社運営に関わるあらゆる事柄をすべて綺麗に決算するのだ。
事務員達にとっては通常業務に加えこの締め業務にも追われる苦しい戦いの一日なのである。
「一緒に行ってくれるって、連れてってくれるって言った……」
その修羅場の中で恨めしげに悲しそうな視線をホッジンズに向ける娘がいた。
自分の服の裾をぎゅっと握り、唇を噛み、『あたしは怒っている』と主張している。
至極色気のある長い黒髪の美女だ。
黄金の林檎とも言える豊かな胸が惜しげも無く披露された前開きのビスチェ、それらは肩から肘にかけてチャコールグレーのインナーと繋がっている。
ビーズチョーカー、ペンダント、バングル、ハンドチェーンブレスレットと貴金属の重ねづけ。青に染色され金の刺繍が入った革のホットパンツ。
足の継ぎ目から伸びた幾何学的な模様を描いた刺繍糸のガーターベルトはニーハイブーツまでの素肌を片足だけさりげなく飾っている。
服装からその艶のある美貌まで何もかもが目に毒な存在だが。
「やだ、やだ! 連れてってくれないとやだ」
やっていることは子どもそのものだった。地団駄を踏んでいる。
「やだって言われてもなぁ……カトレア」
クラウディア・ホッジンズ、このC・H郵便社の社長はそんな彼女の様子に苦笑いをした。
「この書類の山、見てくれ。鈍器になりそう」
ホッジンズの机の上にはまとめれば確かに鈍器になりそうな厚さの書類があった。喋りながらも判子を押している。事務員達が作った各種書類には必ず彼の審査と印が必要なのだろう。 事務員達を信頼しているのか、読む気が失せているのか、内容を確認せずにただひたすら押している。
「ホッジンズ社長、済んだ書類からください。こちらもお願いします」
会話が中断された。積み重なっていた書類に更に書類の山が足される。
「あ、ごめんねラックスちゃん。全部確認してくれた?」
カトレアとホッジンズの間に割り込んだのはあどけない顔をした少女だった。
肩より上で滑らかに切りそろえられたラベンダーグレーの髪の持ち主。
眼鏡をかけてはいるがよくよく見ればその両目の色が左右で違うことがわかる。控え目な印象だが首元のスカーフや横髪につけられた金のバレッタは職業婦人の小さな主張だ。
「しました。訂正があるところは付箋をつけています。そこは見てください」
ラックス・シビュラ、孤島で宗教団体に半神として祭り上げられていた娘がいまは立派にC・H郵便社で働いていた。
「ありがとう。俺の秘書は最高だ。控え目に言っても好きだ」
色男が寄越すウインクに、ラックスは絶望的な表情を返す。
「お世辞はいいので、腕を、腕を動かしてください。社長が遊んでいたつけがこの状態です。あの時……私が社長を止められれば……舞台女優と旅行なんて……どうせすぐ別れるのが目に見えていたのに……あの時、私が……」
「酷い。傷心の俺は更に傷ついたよラックスちゃん」
「……縛り付けてでも業務をしてもらっていたらこんなことには……」
何かの事件に巻き込まれて心を病んでしまった人間のような有様の秘書に、さすがのホッジンズも生真面目さを取り戻した。
「ごめんなさい。俺は判子を押す機械と化すよ」
ラックスは次にカトレアにすがるように言う。
「それとカトレア。お願い……ホッジンズ社長の手を止まらせるようなことをしないで。ホッジンズ社長の仕事の進捗に、皆の退社時間がかかっているのよ。今日こそ早く帰りたい……」
ラックスの言葉にそれぞれの仕事を黙々とやっていた事務員達が一様に頷いた。
事務員達にとって今日いつ会社から解放されるかは大袈裟に言うと死活問題だった。
カトレアは気づかない振りをしていたが、自分の背中に時偶突き刺さる『邪魔者は退去せよ』という無言の圧力の塊に自然と声が萎む。
「何よ……。秘書だからって偉そうにして。社長秘書……ずるい。あたしも秘書やりたい」
「カトレアは自動手記人形でしょ……。そっちの方が素敵じゃない。偉そうになんて……貴方は休みでも私達は仕事中だってだけよ」
見た目は幼いままだが中身はすっかり出来る秘書に成長している。身ひとつで宗教団体から逃げ出して、拾ってくれた会社に、ホッジンズに報いるために努力したのだろう。
「ホッジンズ社長、お菓子は書類を片付けてからにしてください」
机の引き出しから何か取り出そうとした手をホッジンズは引っ込めた。
「何よ何よ何よ! だって自動手記人形は休みが決まってないんだもん仕方ないじゃない」
カトレアは口論を続ける気だったがラックスはいつの間にか電話対応をしていた。カトレアに対して『ごめんね』と目で謝っている。
「……わかってるわよ」
社内が忙しいのは一目瞭然。自分が邪魔者なのもわかっている。それでも、暇を持て余した自動手記人形カトレアは諦めきれない様子で印刷されたチラシを判子を押す機械と化したホッジンズに見せる。
「でも、一年に一度なんだよ。『飛行手紙』に参加できるの。あたし、あたし、もう手紙も書いてきちゃったし、社長が連れてってくれるっていったから他に誰も誘ってないし。ひとりでいくなんてやだ。お祭りでひとりだなんてそんなの罰じゃない」
そこには『第七回航空展覧会』と書かれていた。
開催地はライデンシャフトリヒ陸軍保有の空軍基地演習場。
陸海軍の軍用機、有志から集められた民間機を公開展示すると共に航空演習の披露があるようだ。カトレアの言う『飛行手紙』は演目の一つだ。
民間人から集めた『これを受け取る誰かへの励ましの手紙』を陸海の選ばれた精鋭の操縦手が空から散布するという。参加者は手紙を拾った見知らぬ誰かに激励を送り、また自分も激励を送られるという浪漫のある行事だ。
空から手紙が降ってくる大陸唯一のお祭りでもある。
第六回の開催が数年前であるという記述から、ここしばらくは戦争の激化を理由に中止されていたようだ。
チラシと口づけせよと言わんばかりに近付けられてホッジンズはくしゃみをする。
「俺もね、行きたいんだよカトレア。でも今日が締め日なの忘れてて……」
カトレアの眉が下がる。紫水晶の瞳が悲しそうに歪む。子犬が切なげに鳴いているような様子である。罪悪感がホッジンズの中で芽生えた。
「そんな顔しないで、俺の可愛いお嬢さん。展覧会に絡んだ祭りは夜までやってるから途中で参加は出来るよ。というか従業員も早めに仕事切り上げさせてお祭りに行かせてあげたいし。でも飛行手紙には間に合わない……と思う。いや、わからないけど、うん、たぶん」
「あたし、それまでひとりなの?」
「ベネディクト……は、配送いってるしなあ」
「あいつはいい、何であいつの名前だすの」
カトレアは顔を赤くしながら社長机をひっくり返そうとする。細い腕から想像もつかない腕力だ。ホッジンズは必死に机を押さえた。
「落ち着いてカトレア。わかったから。他に空いている年の近い子は……ラックスちゃん。従業員の業務予定表見せて」
電話をしている最中だったが、ラックスはにこやかに話しながらもホッジンズに手帳を渡す。
そこには丁寧な字で従業員の稼働計画が記されている。ホッジンズはにっこりと笑った。
一人、都合が良さそうな相手を見つけたからだ。
「ああ、ヴァイオレットちゃんが非番だよ」
「え」
カトレアの声音には若干の拒絶が見えた。
樹木が連なる道を進んだ先にその邸宅はある。
様々な品種の花が植えられた豪華絢爛な色彩の花壇、手入れの行き届いた生い茂る芝生。
四季の野菜を育てている畑。
その中に君臨するのが現在パトリック・エヴァーガーデンが当主を務めるエヴァーガーデン邸だ。館というよりは城に近い。白亜の壁に群青の屋根。尖塔から窓に至るまですべてが左右対称になっている優美で均整のとれた造形だ。
カトレアが訪ねると彼女の姿を見つけた庭師が声をかけてきた。
「カトレア・ボードレール様ですね」
ホッジンズが先に話をつけてくれたおかげで門から邸宅までは庭師が送り、玄関では執事が出迎えてもてなしてくれた。
「もうすぐ来られますよ」
控えの間で手持ち無沙汰になりながら待っていると、執事の言う通り程なくしてヴァイオレット・エヴァーガーデンは現れた。
「カトレア……?」
足音を消しがちな分厚い赤絨毯のせいだけではないだろう。
音もなく姿を見せたヴァイオレットは普段の自動手記人形姿とはまた違う装いをしていた。髪は緩く一本に結ばれて顔横に花の髪飾りが揺れている。
白地に青い小花が描かれたカシュクールワンピースは清楚で可憐という言葉がぴったりだ。小花達はただ散りばめられているのではなく肩口から胸元、下へ下へと小花が舞い落ちて裾に積もり重なるように描かれている。
ワンピース一枚でも夏の終わりとはいえ気候が暖かなライデンシャフトリヒでは充分過ごせそうだったが彼女は濃紺のカーディガンを羽織っていた。機械の腕を隠す為だろう。いつものブローチも胸に健在だ。
「へーあんた普段はそんな恰好なんだ。なんか、お嬢様? かわいい。いいなあ」
ヴァイオレットは義母の趣味だと返す。
「それよりもどうされたのですか」
家にまで訪ねてくる案件とは何なのか。早急に答えよ。と碧い瞳が言っている。
「うん、ちょっとね……」
カトレアはホッジンズとの会話を思い出す。書類に判子を押す手を一度止めて、謎に包まれたヴァイオレットの口説き方を彼は教えてくれたのだ。
『いいかい、ヴァイオレットちゃんを誘うなら。こういいなさい。これは俺からの任務だって』
自信ありげな様子だった。
確かにホッジンズと話すヴァイオレットは従順で貞淑な印象だ。
だが、それが他の者にも適用されるかというと違う。
――正直、得体が知れないのよね。この子。
元軍人だというのは知っていた。
カトレアが慕うホッジンズと同じライデンシャフトリヒ陸軍所属であったと。
C・H郵便社の面々は変わり者のホッジンズが集めてきただけに元軍人の過去を持つという経歴はそれほど珍しいものではなかった。
だが、ヴァイオレットは経歴を抜きにしても不思議な存在だった。
笑顔を見せない。言葉は丁寧だが媚を売るような真似は一切しない。
それ故に他者から距離を置かれがちだが孤独を厭う様子は無い。
氷像のように美しいが心の無い存在。カトレアにはそのように見えている。
「あの、さあ……これ、もう決まったことなんだけど」
だからこの魔法の言葉に効果があるのか不安だった。ホッジンズ以外の命令を聞いてくれるのかどうか。聞いてくれたとしても、楽しい時間を過ごせられるのか。
――でも、お祭りに一人で行くよりいいわ。
カトレアは意を決して口を開いた。
「ヴァイオレット。あんた、あたしと一緒にくるのよ。ホッジンズ社長からあんたへの任務なんだけど、社長があたしと合流するまでの間、航空展覧会に同行しなさい」
しなさい、と偉そうに言ってから数秒沈黙が流れた。堅物で無口で無愛想な氷の美女は長い睫毛の上下運動を数回行ってから疑問符を浮かべた顔で言う。
「任務、ですか」
「そうよ。任務よ」
「本当に、任務ですか」
ヴァイオレットの澄んだ碧い瞳に映る狼狽えた自分の姿からカトレアは目を逸らしつつ言う。
「う、そ……だと思うなら社長に聞きなさいよ」
「いえ。今日は締め日で忙しいでしょうから電話は遠慮します。承知致しました。社長の任務とあらば……お受けします」
締め日を気にする辺り、カトレアと違い職場に大人の配慮がある。承諾してもらったものの、カトレアはすぐに不安になった。
あまりにも感情が見えないので機械や妖精、それか幽霊、何か意思疎通の出来ない不確かな存在と会話している気がしてきたのだ。
「ねえ、本当にいっしょに行ってくれるの?」
「はい」
「ほんとのほんと?」
「本当の本当です」
「あんた、何か生きてる感じしないけど生きてるのよね?」
「生きています」
「ついでに聞くけどあんた社長に可愛がられてるけど恋人?」
「違います」
「ベネディクトのことどう思ってる?」
「……ベネディクトですか? 戦闘能力が高いです、意外に統率力もあります」
色々と失礼な物言いだったがヴァイオレットは気にした様子もなくすべて真面目に回答した。
カトレアは諸々の回答で途端に元気が出てきた。喜びに任せてその場で飛び跳ねる。
「利害が一致して満足。そうと決まれば準備ね! おうちの人に今日は出かけるって言ってきてよ。あとヴァイオレット、便箋と封筒と万年筆も用意して。飛行手紙に参加するから」
「……飛行手紙……。確か、陸海の一般公開空軍演習演目の一つですね」
さすが元軍人だけあって詳しい。参加したことはあるのかとカトレアが尋ねるとヴァイオレットは無言で首を横に振った。
「見たことはありませんが、知識として教えて頂いたことがあります……」
それは一体誰に教えて貰ったことだったのか。ヴァイオレットは語らなかった。
「カトレア……便箋等以外に必要なものはありませんか。武器の携帯の許可はホッジンズ社長から出ているのでしょうか」
「武器なんて要らないわよ。何なのあんた。怖いんだけど」
「任務と言われましたので、つい」
ことの成り行きがわかっていないヴァイオレットとそんな彼女に度々戸惑うカトレアではあったが、目出度く二人は出かけることになった。
ライデンシャフトリヒ陸軍保有空軍基地演習場は、首都ライデンより遠く離れた場所に存在した。行き方はそれほど難しくはない。
首都から乗合馬車、乗合運行車に乗るのが最も手軽な方法だろう。
停留所で降りると木々に囲まれた森林地帯が目に入る。
街に慣れている者は一瞬何処に来てしまったのだろうと不安になるほどの緑豊かな場所だが恐れることはない。舗装された林道を看板を頼りに進むと目的地である演習場へ程なくして到着する。平時は一般人の立ち入りは禁止されているが航空展覧会の間は入場規制は無い。
演習場の周囲には許可された飲食店が店を構え、出張屋台をしている。軍事施設が一転して祭りの場に変身していた。会場は老若男女の集いだった。陸海軍関係者の家族、一般参加者、この航空展覧会を見たいが為に遠方よりやって来た熱心な飛行機好きと様々だ。
男女比率としては男性が多い。
ヴァイオレットやカトレアのような若い娘は少数派と言える。
「すごい、広いわね。普段もここで演習してるんだ……見てっ! 戦闘機? あれ戦闘機?」
展示された軍用機達に驚きを隠せないカトレアと。
「あれは偵察機、雷鳥です」
機体名を正確に答えるヴァイオレット。
「陸軍、海軍はそれぞれに空軍を保有していますが名前でどちらの所属かはすぐわかります。陸軍は鳥類の名前をつけています。海軍は海の生物の名前をつけるそうです」
謎の美女達が熱心に軍用機を語る姿は若干奇異に見える。
演習場は普段はれっきとした軍事施設として機能している為立ち入り禁止区域も多く存在した。会場を長方形の箱として空間を捉えると真ん中周辺に軍用機の展示が行われている。
それらを囲むように格納庫、陸軍車両待機場所、民間人用の一般休憩所、この航空展覧会の実地本部、実地本部の高みに設立され天幕に隠された管制塔がある。
こちらは一切中の様子が見えない。実地本部並びに管制塔の付近は広く距離を取ってから柵が敷かれ完全に関係者以外は入れないようになっていた。
実地本部では陸軍の広報がこの航空展覧会の目玉の一つである飛行演習の実況を行っている。
『会場正面上空を御覧ください。六機の戦闘機海蛇が侵入して参ります。縦一列の隊形から菱型に変化していきます。息のあった飛行にご注目ください』
海軍の戦闘機が見事な飛行技術を見せつけながら演習場上空を飛んで過ぎ去っていく。飛行した後には青い空に白い煙が彼らの飛んだ証として残されていた。
『一番機の操縦士はライデンシャフトリヒ、ライデン出身のジュード・ブラッドバーン。二番機の操縦士はプレガンド出身のヘンリー・ガードナー!』
参加者は皆空を見上げ歓声を上げている。熱の入った実況と共に楽団が音楽を奏で場内の雰囲気を更に盛り上げている。
カトレアはあらかじめ持っていたチラシを開き、いま現在披露されている機体の演習時刻を確認した。規定された時間通りに進行しているようだ。
飛行手紙はまだまだ先の行事になっている。
戦闘機の曲芸飛行に目を奪われていたヴァイオレットの腕を掴んだ。
「ね、飛行手紙の回収はまだ先みたいだから屋台で何か買って、食べながら見ましょうよ。これずっと続くみたいよ、飛行演習。ヴァイオレット、食べたいものある?」
「食料の確保ですか。なら味の好みを優先するより保存食に適したもののほうがいいのでは」
ヴァイオレットはカトレアを見ずに飛行している機体に合わせて首を動かしている。
カトレアはそんなヴァイオレットの顔に指先を近づけた。
ヴァイオレットが首を捻ると自動的に頬に指が刺さる。ふにゃりとした感触がした。
「ヴァイオレット、あたしを見なさい」
掴んだ手は硬質なのに、頬は柔らかい。
――不思議で、ちょっと不気味。
しかしカトレアはどこか安心した。
この娘にも柔らかい部分があるのだと知れたからだ。
「やめてください」
拒絶であっても、ヴァイオレットから反応が貰えると嬉しくなってきた。
「やーよ。あんたがあたしの方を見てくれないからお仕置きよ。ねえ、あんたなんか勘違いしてる気がするけどこれ任務って言っても遊びだからね。保存食なんていらないわよ」
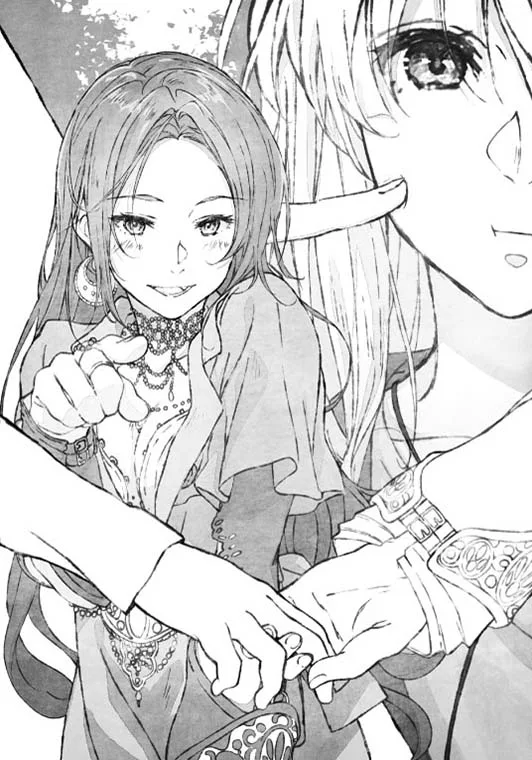
「遊び……?」
「あんた、ラックスとは偶に遊んでるらしいじゃない。ほら、お茶したり」
「ああ、はい。お茶してます」
「それよ。それをあたしとするの。ご飯たべて、お喋りして、それでお祭りに参加して。しばらくしたら会社の皆も仕事切り上げてくるみたいだからその後は合流しましょ」
「……任務、なのですよね?」
「任務よ。すごく任務。ものすごく任務」
念を押して確認してくるヴァイオレットをカトレアは無理やり屋台方面に歩かせる。
「遊ぶ、とは具体的にどんな任務なのか内容の提示を求めます」
「なんか難しく言ってるけど遊び慣れてないんでしょ。いいわよ、お姉さんが教えてあげようじゃない」
ヴァイオレットは、繋がれた手を不思議そうに眺めた。それでも手を振りほどくことはせず、鳥の雛のようにカトレアの後ろをついて歩いた。
出張屋台の食べ物を端から端まで見て回り、両手に持ちきれないほど買いつくし二人で分け合った。飛んで行く戦闘機を追いかけて走り回る子ども達を見て目を細め、女二人だからと軽々しく声をかけてくる輩を手ひどく振り、陸軍広報の実況に感心しながら去っていく軍用機の数々に拍手をする。移動遊園地と呼ばれる回転木馬やダーツなどの遊具も子どもに交ざって体験してみた。最初こそ性格が掴めないヴァイオレットに身構えていたカトレアだったが、持ち前の人懐っこさと豪快さで彼女との時間の楽しみ方を見出していた。
「カトレア、待ってください。カトレア」
「ねえ、これ美味しい。すごく美味しい。はい口開けて」
「食べたくありません」
「任務だから口開けて」
「……任務だと言えば何でも従うと思ってはいませんか?」
「あーん。ほら落ちちゃう。落ちたらあんたのせい」
意外と押しに弱いので、振り回しながら連れ歩くと年下の女の子として可愛く思えてきたのである。お姉さん風を吹かせられるのもカトレアとしては好ましいところだった。ひとしきり遊んだところで、二人は休憩することにした。夏の終わりとは言え、外で長時間日差しを浴びれば疲労は増える。大きな天幕が連なり一般参加者が日差しを防いで涼んでいる休憩所のベンチに腰掛けた。そこからも飛行演習の様子は眺めることが出来た。
「まだ?」
「……明確に相手がわからない手紙。しかも励まし……自動手記人形の手腕が問われます」
ヴァイオレットは飛行手紙に出す手紙を書いている。
かき集められた手紙が操縦士に渡され、会場上空から飛行機によってばら撒かれる。手紙の配達人となるプロペラ式の軽飛行機は既に手紙の回収を始めていた。操縦士に子どもと女性が群がり一躍時の人となっている。真黄色の機体は青い空によく映えることだろう。
自分は手紙を書き終えていたカトレアは手持ち無沙汰になりヴァイオレットにちょっかいをかけていた。ヴァイオレットは段々とかわすのがうまくなってきている。構われたいカトレアは口を尖らせて言う。
「ねえ、そんなの誰が書いたかわからないんだがら好きなこと書けばいいのよ」
「……だめです。書き直します」
ヴァイオレットは一度書いた手紙を封筒にしまいこんでしまった。また新しく便箋を取り出すが一文字目も書けない様子だ。
「カトレアは何と書かれたんですか」
教えを乞うように問われて、カトレアは豊満な胸を更に張って答えた。
「あたしの手紙を拾って貴方は幸運ね。きっといいことあるわよ。なくたって死なないわ」
「そう書いたのですか」
「そうよ」
カトレアらしいといえばらしい。だがヴァイオレットの参考にはならなかったようだ。
「なによー、あんた仕事以外で手紙とか書かないわけ? そんな困ることかしら」
「……私用の手紙は、随分前に書くのを止めてしまいました。仕事でしか書いていません」
ヴァイオレットの僅かな表情の変化を、カトレアは一瞬だが捉えた。人との距離が元来近い体質の娘ではあるが更にヴァイオレットとの距離を縮める。
「その話題面白そう。何で? 話しなさい」
ヴァイオレットは距離をとった。カトレアが縮める。ヴァイオレットがまた距離をとる。
最終的にベンチの端に二人ぴったりくっつく形となった。
「……何故ですか」
「面白そうだから。どうして書くのをやめたの? 当ててあげよっか。相手は男の子でしょ。それも特別な人だ。親兄弟以外の、一番気になる男の子だ」
「…………どうして性別がわかるんですか」
ヴァイオレットが初めてカトレアをまじまじと見た。
「あんたの客層とあたしの客層って違うのよ。あたしのお客さんって……若くて、恋文が多いの。それも恋する乙女ってやつよ。彼を振り向かせるにはどうしたらいいの、とか。女心がわからない、どうしたら彼女は振り向いてくれるんだとか。よく相談を受けるわけよ」
「……肩を叩いて名前を呼べばいいのではなく?」
そういう意味ではない、とカトレアがヴァイオレットの額を指先で弾く。
「ねえ、どんなひと。あんたの好きな人って」
「そ、ういう方ではない、と」
「じゃあ嫌いなの」
「そんな、そんなことは」
カトレアは笑みが浮かぶのを抑えられなかった。
――どうしよう。いじるの面白い。
堅物で無口で無表情の謎の女、ヴァイオレット・エヴァーガーデン。
動揺などしない鉄の女。それが自分の一言で崩れようとしている。
「じゃあ好きしかないじゃない。ふつう、とかじゃないでしょ。その顔は違うわ。あたしを舐めないで。こちとらこの恋愛相談込みの代筆でお金稼いでんのよ」
ヴァイオレットは口を開けては閉じ、目を右往左往させて戸惑いを示す。
――心を入れられたばかりの人形みたい。変なの。
カトレアはヴァイオレットの過去も何も知らないが故に、あるがままに年頃の女の子として接する。
「ねえ、ねえったら」
ただ、仲良くなりたいだけなのだ。
「ねえ、どんなひとなの」
ヴァイオレットにしている行為がどんなことかも知らずに無邪気に。
「…………」
開こうとしている箱の中に入っているのは、宝石だと信じている。
「何て呼んでたのよ」
ヴァイオレット・エヴァーガーデンの心の箱に入っているのは。
「少佐です」
入っているのは。
「少佐。かっこいいじゃない。軍人なんだ。あんた元軍人だもんね。少佐は何歳? 見た目は?」
入っているのは、宝石とは限らない。
「……聞いたことがありませんでした。恐らくは三十代になっていたと」
「うっそ。かなり年上……社長と同じくらい? 歳の差なんだ……」
ヴァイオレットは久しくその人について語ったことはなかった。
「カトレアの髪とはまた色味が違う、黒髪で……」
存在を話すことはあるが深く掘り下げはしない。共通の知り合いでもあるクラウディア・ホッジンズとも彼の話題は互いに触れないようにしている。
ヴァイオレットは何も書かれていない文面から、雑踏に視線を移した。かつては自分も纏っていた紫黒の制服の軍人がその中に混じっている。
戦争は終わり、空は快晴で、もう文字を知らなかったあの日々ではないのに。
雑踏が、軍靴の音が、あのランタンの街に居た時の少女兵に戻してしまう。
いつまでも、いつまでも、追うのはただ一人。
「エメラルドグリーンの瞳で……」
とてもうつくしいひとで。
「私を拾い、育て、使ってくれました」
道具と主人で。
「でも、もう居ないんです」
道具なのに守れなかった。
『ギルベルトは死んだ』
ホッジンズの言葉が呪いにも似た重さと苦しみを伴って、何度も何度もヴァイオレットの頭の中で再生される。
「少佐はどこか遠くへ行ったの?」
「……はい、遠くへ行きました。帰って、きません」
「まだ待ってるの?」
「……まだ」
カトレアの質問にヴァイオレットは否が応でも考えてしまう。
「待っています」
わからないと言って拒絶し、返せなかったあの日の返事を。
「止めろと、もう、待つのを止めろとたくさん言われました。ですが、どうしたって、私は、私は……」
『愛してる』
『愛してる、ヴァイオレット』
『聞いて、いるか』
『君が、好きだ』
『ヴァイオレット、愛、は』
『愛とは、君を一番守りたいと思うことだ』
「少佐が、来てくださるのを待ってしまうんです」
痛みに耐えているかのような顔をした。それはカトレアが見た中で、一番ヴァイオレットが人間らしい表情を見せた瞬間だった。この不器用な娘が発する小さな変化。喜怒哀楽が豊かな者からすれば心の現れとも言えない静かな動き。
――嗚呼。
カトレアの中で啓示が降りてきた。まだ親しくもない。友達でもない。
彼女の何を知るわけでもないが、わかった気がした。
――心の嬉しい部分がほとんど持っていかれてるからなんだ。
だからこんなに感情が少ないのだろうか、とカトレアは考えた。
「あんた、いない人に恋しているんだ」
カトレアが突いた藪の中は想像とは違う深い森の扉だった。
「恋……?」
森の奥で彷徨っている娘本人はどうして迷っているのかもわかっていない。目隠しをされたまま、取り方もわからず、手探りで生きて、放置されている。
カトレアは申し訳なく思った。本当はこんなところで聞く話ではなかったのだ。
「恋……とは」
心を持っていかれたドールは、この年下の同僚は、恋が何かもわかっていない。
「いや、もう愛だよね」
「あ、い……?」
二人が訪れた時より演習場は人が増えていた。雑踏は騒がしさが増すばかりだ。カトレアは歩いて行く人々を指差す。性別も年齢も違う。それぞれに目に見えぬ葛藤に溢れた人生がある。
「家族、友達、兄弟、仲間、いろいろあるけどさ。あんたのは、恋愛の愛だよ」
仲睦まじい恋人達は手本のように何処もかしこも存在している。恋愛は、ごく自然に世界に溢れていた。だが、ヴァイオレットは否定した。首を振り、眉を下げ、唇を噛む。
「恋愛なんて、私、出来ません」
頑なに拒絶する。
「してるじゃん」
「いえ、出来ません。わかりません」
はたから見れば言い争いをしている風に見えただろう。喧嘩ではなかったがお互い一歩も引かなかった。愛だと言う者と。愛ではないと言う者。両者は相容れない。
カトレアは苛立ちを滲ませながら、それでも食い下がる。
「そんなの、あたしだってこういうものだって言えないよ。愛って不確かで、恋ってよくわかんない。でもしてる時はわかるの。してる人だって見たらわかる。あんたのはそうだよ。たとえいまは会えない人でもさ……」
会えない人、という言葉がカトレアの唇から発せられたところでヴァイオレットの碧眼は悲しげに揺れた。他人の口から聞かされる言葉は、自分に言い聞かせるより遥かに重くのしかかってくるものだ。
ほら、そんな顔を見せる癖にどうして、と誰もが諭してしまいそうな表情を時折するのに。
「いいえ……出来ません。本当に、出来ないんです……少佐は……」
ヴァイオレットはやはり否定する。
長い金糸の睫毛が伏せられた。ヴァイオレットが俯く時、視線は胸元へ行く。そこにはいつもエメラルドのブローチがある。それは煌々と輝き、色褪せることはない。
月虹眩しい春も。緑雨流れる夏も。金風吹き荒ぶ秋も。霜夜凍てつく冬も。
「少佐、は」
ヴァイオレットの中のギルベルト・ブーゲンビリアという男の存在のように。
けして、色褪せることはない。
「少佐は死んでしまったんです」
その瞬間囁かれた言の葉は、とても残酷なものだった。
カトレアとヴァイオレットの間に流れる時間の針が一度止まった。
実際はそんなことは起こり得ない。だが、まるで本当に時が止まったかのように二人とも身動きをしなかった。瞬きも呼吸も、一瞬だけ世界の時間軸から刈り取られた。ようやく流れだした時には間抜けな返ししかカトレアには出来なかった。
「え、え?」
声が裏返る。
「死んでいるんです。少佐は。私が、守れなくて、死んでしまったんです。私は道具で、盾で、剣だったのに」
カトレアの背中から冷や汗がじわりと流れた。
――居ないどころか、死んだ人に、心を奪われてるの?
カトレアは冗談でしょ、と言うがそれに対するヴァイオレットからの返答はない。
無理やり作ろうとした笑顔は失敗して半笑いになった。顔がひきつる。いままで言ってきた自分の言葉の無神経さに、息が詰まって唾がうまく飲み込めない。
「ヴァイオレット、その人、大戦で……亡くなったの?」
「はい」
「本当に?」
「そう言われています。私には……このブローチが遺品として残りました」
カトレアと出逢った時からそれはヴァイオレットの胸に輝いていた。その機械の指先が、偶にそれに触れるのを何度か目撃している。何かのお守りなのかとばかり思っていた。
もっと矢継ぎ早に色々と言いたかったが、態度はつい慎重になる。ざわめき立つのだ。
「でも、あんた、信じて、ない……わよね?」
嫌な予感にも似たざわめきが立って、カトレアの全身を蠢く。
「……」
ヴァイオレットにとって、この問いへの答えは禁忌だったのかもしれない。
「ねえ、正直に言いなさいよ」
黙りこんでしまった彼女の横顔、無表情にしか見えなかったそれはいまでは寂しげなものとしてカトレアの目に映る。
「……私は」
嫌なざわめきは体中を這いずり回り、それを吐き出したくて、堪らない。
「あんた、信じてないんでしょ? 待ってるって、あんたが言ったんだよ」
答えを知りたい。
「けれど、ホッジンズ社長が」
「いいから、自分の思ってること言いなさいって」
ヴァイオレットは。
「はい……」
断罪を受け入れた罪人のように。
「私は……」
咎を告白した。
「少佐は、生きていると、思っています」
それは一体どれくらいの間思い続けてきたことなのか。
もしかしたら、初めて死を告げられた時からそうだったのかもしれない。
悲しみに暮れても、現実がすがる希望を砕こうとしても。
それでも否定していたのかもしれない。彼の人は生きていると。
「あんた、あんた……」
何をやっているんだ、とカトレアは叫びたくなった。
遠く離れた人を恋い焦がれるのと、故人を盲目に愛すのとでは意味が違う。距離は努力でつめることが出来る。カトレアとヴァイオレットのように。だが、死人はけして戻らない。
「あんたが言っていることは、腕を取り戻したいって言ってるのと同じだよ!」
そんな不毛なことをして、美しい姿を他の誰かに愛でてもらうこともせず、死者の生存を信じてただ無闇に時を過ごすなんて。勿体無い、いますぐやめろと説教をしたくなった。
腕も、好いた男も、代替がある。
「この先もずっとそうして生きていくつもりなの? あんた、ね、ヴァイオレット……」
「わかっています」
ヴァイオレットは、はっきりと言った。
「無駄なことです。意味がありません。価値がありません。でも、少佐が居ない私も、そうなのです。意味が、ありません」
「他の人じゃ駄目? いまは辛くたっていつかは絶対思い出になるよ、それなら早い内に……」
「いいえ……いいえ」
それはまるですべての生き物に対しての宣戦布告だった。
「私には、ギルベルト・ブーゲンビリア少佐しかいないのです」
カトレアは口が開いたまま固まってしまった。
上空では人気の機体が通り過ぎたのか周りで歓声が沸き起こっている。此処に居るのに、此処に居ない。そんな奇妙な感覚を碧の瞳の強い視線がもたらす。
――何なの、この子。
どうしてこうも、切り裂くように、人を切なくさせてくれるのか。
カトレアとは価値観が違いすぎた。行き場のない、気持ちが胸に渦巻いて苦しい。
「私のこの行為が、人を不快にさせてしまっているのは理解しています」
何をどう生きてきたらこんな頑固に育つのか。
「どうか無視してください。放って置いて……ください」
「あんたって、馬鹿でしょ……」
幾星霜、不毛だと謗られ愚か者の烙印を押されたとしても。彼女は信じるのだろう。誰かが無駄だやめろと言っても耳を傾くことはあれど。
「はい。私は、馬鹿で……愚かです」
ただ一人しか欲しがらない。カトレアは額に手を当てて犬のように唸った。考え事をしすぎると熱くなり、痛くなるのだ。いまは代筆の文章を捻り出す時より熱が灯っている。
――駄目だ。これ。
彼女はいつも、いつも、願いを込めていたのだ。
――頭良くないあたしでもわかる。
逢いたい、逢いたい、と。
――崖で泣いてる子を落とすと脅すようなものだわ。
ブローチを握りしめて祈っていたのだ。
――責めちゃいけないんだ。
この愚かさが、ヴァイオレット・エヴァーガーデンなのだ。
口から銀の毒を吐き出すような辛さでカトレアは言った。
「わかった。あたしもわかった。あんたは、馬鹿だけど、でも……………………それ、やめたほうがいいなあと思うけど……ほんと思うけど、仕方ないとこもある、と、思う」
碧眼の輝きが変わった。
「本当ですか。ホッジンズ社長にはやめろと言われています」
ヴァイオレットの肩をぽんと叩いた。本当はホッジンズに同意したかったが、自分くらいは味方で居てやりたかった。
「だって、生きるのに愛って必要だもん。愛って嬉しいことの象徴みたいなもんじゃない。結婚して、どっちか死んじゃって……でもその人の思い出をたよりにして、とかさ。別に恋愛じゃなくても……貰った愛って消えないよ……親とかもさ、あたし、家出してホッジンズ社長に拾われたんだけど。こっち、知り合いいなくて寂しい時多くて。酷い親だったけど、頭撫でられたこととか、そういうのは、寂しい時にいつまで経っても思い出す……」
カトレアの事情を知らなかったヴァイオレットは、『そうなのですか』と言葉を返す。二人はいまようやく向かい合って話していた。一方通行ではない語らいだ。
「愛は、必要、ですか」
「必要だよ。何を頼りに生きるの。いままでの人生で優しくされたり、貰って嬉しかった物や言葉、あるでしょ。そういうの、あんたの中に溜まっていくから、あんた生きていけるんだよ」
「で、も」
言葉を途切らせ、ヴァイオレットは言う。
「何もなくたって、私、生きてました」
カトレアは首を横に傾けた。どういう意味かわからなかった。
「いまも、生きています。少佐のことは忘れられません。ですが、これは愛ではありません」
ヴァイオレットが孤島で一人で生きてきたことをカトレアは知らなかった。何もなく生きてきたというのは少佐と知り合う前の時代のことだろうかと勝手に推測する。
「ヴァイオレット……ねえ」
「私は、違うんです。道具なので、そういうものは本来……」
「聞いてって。道具って、何言ってんのよ。あんた、元軍人だから? 兵士が道具って言うの?あんた、国を守ってくれた人達に失礼じゃない」
「違います。そうではなく、もっと根幹から私は……道具でいたから、道具で、いないと……」
うまく表現することが出来ないのか、ヴァイオレットは機械の指先をぎゅっと握りしめる。
「少佐に必要として貰えません」
握りしめたまま、緩く解くことが出来ない。
「私は人ではないんです。道具でいないと、駄目なのです。道具でいないと……うまく戦えません。少佐の傍にいたいと思う資格も、失ってしまう。少佐の傍に居たいと思うには、誰かの道具でいるには、そういうのは……阻害されなくてはいけないんです」
傾けたままだったカトレアの首は横へ、横へと更に傾き危うくベンチから落ちそうになった。
「……待って、整理したい」
掌を少し上げて、制止の姿勢をとる。
「はい」
ヴァイオレットは素直に従った。
カトレアが整理するのを待つ。カトレアはまた犬の如く唸り、唸り、ようやく纏まると指先をびしりとヴァイオレットの鼻先に突きつけた。
「あんたの少佐は死んでる」
「……はい」
「でも好きでずっと待ってる。生きてるって信じてる」
「…………生きてることを信じています」
「あたしはそれを愛だと思う。あんたは恋もしてるよ。でもあんたは違うと言う……死んじゃってる少佐に必要とされなくなるかもしれないから」
「はい」
「愛を知らない……道具でありたいって無理してる。それが一緒に居られる方法だから……何を言ってるのかあたし、わかんない。あんた、ヴァイオレット、だって戦う必要もうないでしょ? 少佐は死んじゃったんだし、あんた軍人じゃないじゃん」
「……はい」
それはヴァイオレットにとって好ましくない事実なのか、返事は小さい。
「軍から離れて、それでいま、うちで働いてる、のよね? 愛はいらない。愛じゃないって拒絶する理由が無くなってるのわかってる?」
「……わかって……い、ます」
それきりヴァイオレットは黙りこんだ。何と言えばいいのか思案している。
カトレアに突きつけられたままの指先から目を逸らし、しばらく俯いてから顔を上げた。
ようやく口を開こうとしたところでヴァイオレットは突然目を大きく見開いた。
何かを見つけたのだ。
大きな碧い宝石の瞳に映しだされたのは背の高い男性だった。
男は人混みの中に浮いては消え、浮いては消える。
手が自然と伸びた。
「……さ」
ヴァイオレットは、とても小さな声で、震える唇で何かを言った。
男は黒い艶やかな髪の持ち主だった。
「ねえ……黙ってたらわかんないわよ。じゃあ何で、自分のこと道具だなんて言うの」
相手の返事を待ちきれなくなったカトレアがしびれを切らして話しかけた。
するとヴァイオレットが突然立ち上がった。
真剣な横顔にカトレアは驚く。
「……ご、ごめん。怒った?」
恐る恐る聞くが、ヴァイオレットは『いいえ』と返す。
「…………………もし」
心此処にあらずな様子でヴァイオレットはベンチから一歩、二歩、と離れて雑踏の方へ吸い寄せられる。
「ヴァイオレット?」
名前を呼ばれ、ヴァイオレットは一度カトレアの方へ振り返った。
「もし、あの方が生きていて、私を必要とされた時に……うまく機能する為です。カトレア、少し席を外します」
もう先程までの幽鬼のような虚ろな顔つきでは無い。
「え、ちょっと……! 何処行くの!」
「追いかけなくてはいけないんです。任務には必ず戻ります」
「誰を!?」
カトレアを置いて、それでも追いかけなくてはいけない相手とは誰なのか。
慌ててカトレアも立ち上がる。だが荷物や手紙が足元に転がり落ちてしまった。
「私の、元の使い手です」
それだけ言うと、ヴァイオレットも人混みに紛れて消えた。カトレアは立ったまま呆ける。
「え、少佐?」
ようやく、それが誰なのか思い至ったが。
「ヴァイオレット、ねえ、ちょっと」
しかし時既に遅し。もう彼女は居なくなっていた。静かで儚げで、足などまるで速くなさそうなのに身のこなしは軍人だった。
「……あたしひとりぼっちなんだけど」
寂しさよりも、驚きの方が勝っていたがカトレアはぼやいた。仕方なく落としてしまった荷物や散らばった物達を拾う。万年筆、便箋、封筒、自分が書いた手紙。そして。
「……あ」
足元にまだ手紙が落ちているのを見つけた。カトレアのではない。
「……」
ヴァイオレットの書きかけの手紙だ。
封筒に収めて、そのまま膝に置いていた。うまく書けないと言って出すのを止めた物だ。
書いていた時は気付かなかったが手に取ると随分と綺麗な一品だとカトレアは思った。
自動手記人形が代筆に使う便箋や封筒は大方が所属する会社で大量生産された物が多い。
それでも勿論お客様に手にとって頂くにふさわしい物を用意してはいるがヴァイオレットが家から持ちだしてきた物は明らかに品質が違った。
手触りの良い真白の紙に銀色の薔薇の縁取りが描かれている。
恐らくは自費で購入したものだろう。
――私用ではもう手紙は書かないって言ってた癖に。
手紙を書く習慣があるものならわかる。
これはとっておきの品だと。手に届いた相手に、その便箋の、封筒の素晴らしさから既に相手への敬意が伝わるように選ぶのだ。
高価な物だから良いとは限らない。
選ばれたものは、見ただけで異彩を放っている。
カトレアはヴァイオレットが居なくなった方向を見る。
もうそこに金糸の髪を揺らして走る娘の姿は無い。
「あたしを独りにした罰よ」
意地悪心と、好奇心で、カトレアは中の文面を読んでみることにした。
後で、宣言通り本当に戻ってきてくれたなら中身のことでからかってやろう。
うまく書けないと言っていたからつまらない内容に違いない。
そう思って、便箋に目を通したのだが。
「……馬鹿な子」
中身はカトレアが期待したようなものではなかった。
便箋はたった一枚だったのですぐに読み終えた。ヴァイオレットが書いた文字をカトレアは指先ですっとなぞる。
――何でかなあ。何で、こう、人の心を。
そこに書かれていたことはカトレアにとって全くの他人事だった。
今日ようやく話せるようになったばかりの人間の事情だ。感情移入するのにも限界がある。
――抉るような、言葉で書くかなあ。
限界があるのだが、紫水晶の瞳にはじんわりと涙の膜が張られてしまう。
今日、ヴァイオレットが自分に語ったこと。それをどんな気持ちで言ったのか、どんな思いでいままで生きてきたのかと想像を巡らせると、もう堪らなかった。
その手紙には、こう書かれていた。
『お元気ですか。
お変わりないですか。
いま、何処にいらっしゃいますか。
困ったことはありませんか。
春も夏も秋も冬も過ぎて、何度も巡りますが、貴方がいる季節だけが来ません。
起きる時、眠りにつく時、意識がおぼろげな時は姿を探してしまいます。
私は夢をほとんど見ないのでお姿を忘れてしまいそうです。
繰り返し、繰り返し、貴方の記憶を頭の中で再生しています。
本当に、もう何処にもいらっしゃらないのでしょうか。
世界中、たくさん歩きました。
色んな国に行きました。
貴方が何処にもいません。
見つかりません。
探しています。
貴方は死んだと、言われても探しています。
命令は守っています。
生きています。
生きて、生きて、生きて。
生きた先に何があるのか。
わからなくても、ただ生きて。
それでも』
ヴァイオレットは、黒髪の男の腕を後ろから掴んだ。
「お待ちください」
振り返った男はブーゲンビリアに伝わる翠の瞳を持っていた。
「飛行手紙と自動手記人形 後編」
街も、村も、森の中も、業風に吹かれて人々がその凄さに笑い声をあげていた。
吹き荒ぶ風の音は天籟の調べ。蒼海の空は日輪の恩恵を用いて地上を祝福している。
その日は午後から夕方にかけて急に風が強くなっていた。勢いをました風というものはまるで龍の如く身体をうねらせながら大地を蹂躙していく。風の龍が通った後は葉音と鳥と虫の音が大合唱を奏でる。
森に囲まれたライデンシャフトリヒ陸軍保有空軍基地演習場も風の遊び場になっていた。
今日という特別な日の為に何度も往復を繰り返している乗合運行車はこれから遅れて参加する客をどっさりと吐き出した。空になった身体でまた街へと戻っていく。降り立った人々は同行者と互いに楽しいお喋りをしながら林道を抜けた。木々の道を歩く時点で空を舞う戦闘機の重厚な旋回音にどよめきや歓びの声が上がる。
第七回航空展覧会が開催されていた。その中に、クラウディア・ホッジンズが率いるC・H郵便社の面々の姿もあった。事務所に居た内勤の者から配達が終わったポストマンまで開放感に包まれた顔で歩いている。
「……」
「機嫌直してよ、ラックスちゃん」
皆が楽しそうにしている中で、ラックスだけが仏頂面だった。
秘書の少女に三十過ぎの社長が必死に笑顔を見せて貰おうと話しかけていた。
自分でも子どもだなと思いつつ、ラックスは心の中の割り切れない感情を吐き出す。
「いいえ、機嫌が悪いとかではないんです。私が……私が必死に頼んでもどうにもならなかったことが……社長のひと声で解決したことで……世の中の仕組みをまた知ってしまい、大人の階段を上っているだけなんです……世の中って……」
「役所に締め切り伸ばして貰ったのそんなに駄目だった? でも、ほら。こうして事務の皆をお祭りに連れて行くこと出来たし。皆、これに行きたいが為に仕事頑張ってくれていたから俺もなんとかしたくて……」
「でも、あの役所の受付の女性ってホッジンズ社長の元恋人なんですよね」
「ああ……まあ、そうだったかな」
本当は恋人と呼べるような仲でも無かったが互いの素肌は知っていたので曖昧に答える。
「つまりそういう情のある関係だからまかり通っている事案だった訳で……だから、私がお願いしても駄目だった訳で……だから……」
ホッジンズは百面相をするラックスを最初は心配で眺めつつも次第に面白くなってしまい笑う。仕事はかなり出来るようになったが、まだまだ人間関係の機微には疎く、それ故に純粋すぎるこの少女のいとけなさが愛らしかった。
「ラックスちゃん。こんなんで怯んでたら駄目駄目。俺の秘書なんだからこれからもどんどん俺の汚い手の内を覚えて貰うよ。社長の言うことは?」
「ぜ、絶対……です」
何を覚えさせているのか。
「元気が無い。もう一度。社長の言うことは?」
「ぜ、ぜったいです!」
ホッジンズはラックスの頭を満足気に撫でた。
「ラックスちゃんは可愛いなあ。俺が立派な社会人に育ててあげるからね」
犬猫にするように愛撫し続けていたら他の事務員からその手を掴まれた。
「社長、それ捕まりますよ。軍警察に」
「ラックスも社長の言いなりになっちゃ駄目。事務の期待の星なんだから社長を刺すつもりで嫌なことには戦いなさい」
「みんな酷くない?」
郵便社の皆が笑ったので自然とラックスも笑ってしまった。ホッジンズはそれを見てようやく内心ほっとする。女性が暗い顔をしているのは苦手だった。
――さて、もう一人心配な女の子は、と。
ラックスに皆に好きな物を買ってあげてと自分の財布からいくらか軍資金を預けて、ホッジンズはカトレアとヴァイオレットを探すことにした。歩いていれば見つかるだろうと誰かが言っていたが、飛行手紙を直前に控え来場客数は最高値を叩き出している。軍事演習場なだけあって広さもあるので難しいと思われた。
――仲良くなってくれたらと焚き付けたけど成功しているかな。
ラックスとヴァイオレットとは違って友情を育めるか成功率が問われる組み合わせではあった。だがホッジンズは自分とギルベルトという成功例があるので二人は意外と良き友人になれるのではと懸けてみたかったのだ。
「……」
ギルベルトと自分はいま絶縁状態にあるのだが、それは考えないことにした。
ホッジンズは無闇に歩くことはせずに一般休憩所へと一直線に向かった。カトレアが会社から出かけてから数時間が経っている。あらかたの見世物や屋台は堪能した頃合いだろう。こういう時に長身は役立つものだと実感する。カトレアを見つけるのにはそう時間がかからなかった。あの鮮烈で華美とも言える美女が目立たない訳がない。カトレアはベンチに寂しそうに一人で座っていた。
「……失敗したか」
遠くから『おおい』と声をかけようとしたところで、別の男が先にカトレアに話しかけた。無視を決め込んだカトレアの腕に無理やり触れて立たせようとしている。一緒に祭りを歩こうと誘っているのだろう。
「まずいぞ……」
ホッジンズはカトレアの心配はしていなかった。早歩きで混雑をかき分けて進む。
「馴れ馴れしく触らないで!」
甲高い声で叫んだのを聞いて、堪らず人を押しのけた。しかしホッジンズの救出は一歩遅かった。カトレアは毅然として立ち上がり、掴まれた腕を逆に捻って拘束を素早く解いてから男の胸ぐらを掴んで股間に膝蹴りを喰らわしていた。
想像を絶する痛みだったのだろう。男はそのまま地に伏せて動かない。カトレアは更に追撃を加えようとしていたのでホッジンズは声で制止した。
「カトレア、こっちにおいで!」
「…………あ、社長!」
嬉しそうに手を広げてこちらに走ってきた。ホッジンズは呆れ笑いをしながら同じく両手を広げた。カトレアが胸の中に飛び込んでくる。周囲の視線が痛かったがカトレアの精神状態を優先させた。一度優しく抱きしめてから身体を離し、大丈夫かと問うと満面の笑みが返された。
「間に合わなかったか……」
「社長、助けてくれようとしてたの? あたし負けないわよ。でも、そっか……こういう時しおらしくしてたら社長が助けてくれるんだ。あと数秒放置してればよかった」
「いや、うん。そうだね」
助けようとしたのは男の方だったとは言わなかった。
「でもね、カトレア。こういう時は穏便に解決しなさいって俺言ったはずなんだけどな……」
「拳を使わなかったわ。元拳闘士として一般人にそれはどうかと思って、足にした。あたし、足はそんなに強くないから。褒めて褒めて社長」
カトレア・ボードレールという娘は、一見幾人もの男を手玉に取ってきたかのような艶めかしい美女であるのに中身は子犬のような娘だった。無邪気で天真爛漫、やることに悪意がないのでたちが悪い。なまじ腕っぷしに自信があるせいか、力で解決しようとする癖があった。
「変な男に引っかからないのは偉いけど過剰防衛は駄目だから減点。此処を離れよう。人目がある」
「褒めてよぅ……あ、うん……でも」
倒れたままだった男は、二人が話している間に地面を這いずりながら逃げ出していた。その姿を一瞥してからカトレアはホッジンズに向き合う。
「あたし此処にいなきゃ。ヴァイオレットがどっか行っちゃったの。でも戻って来るって言ってたから。あたしが此処を離れると入れ違いになっちゃう」
「何処かへ行った……って、行方がわからないのか?」
「そう。たぶん、『少佐』って人を追いかけたんだと思うだけど……」
カトレアの言葉にホッジンズが声を失った。驚愕の表情を浮かべてから、わなわなと震え手でカトレアの肩をがしりと掴む。
「黒髪の軍服の男!?」
ホッジンズがこのように大きな声を出すことは珍しかった。カトレアは彼からの動揺が感染したのか自身もうろたえる。
「わ、わかんない。あたしは見てないの。でもヴァイオレットは自分の昔の使い手だって言ってた」
「どっちに行った!?」
「あ、あっち……でも居なくなってから時間経ってるわよ」
怖い剣幕に押されて、カトレアの群衆を指差す手もか弱く揺れた。
「俺が追いかける。連れ戻すから。ごめんカトレア、社の皆は飛行手紙の回収場所に向かっているからそっちと合流してくれ」
「え、ええ、あたしまた独りなの?」
「いい子だからそっち行ってなさい! いいね! あと絡まれても無闇に戦うんじゃない!」
「……社長!」
すがるように追いかけようとしたカトレアだったが、途中で諦めた。何だか疲れてしまったのだ。本日二度目の誰かの走る背中を眺めてため息も出てしまった。
親の代わりのように面倒を見てくれているホッジンズの言うことに逆らうことも出来ないカトレアは仕方なくとぼとぼと歩き出す。自分も誰かに追いかけてもらえる存在になれたらいいのにと、またも寂しくなってしまった。
「……」
今日は良い日か、悪い日か、どちらなのだろうと考える。
ヴァイオレットと少し話せるようになったのは加点に値する。彼女が自分を置いて行ってしまったことは減点だ。もうすぐ社の皆と合流すれば寂しくはない。加点に値する。だがホッジンズが自分よりヴァイオレットを優先したのは減点だ。
総合的に、気持ちの浮き沈みで評価するといまの状態では悪い日だと言える。
「……」
独りぼっちが嫌なのは、自分に魅力がないと感じるからだ。魅力的な人は自然と周囲に人が集まる。ホッジンズがそうだ。蜜に集まる蝶のようにカトレアも惹かれた。けれどもカトレアは自分はホッジンズのようにはなれないとわかっていた。
唇を軽く噛んだ。心がしおれていく。
とても素敵な一日になるはずだとひと月も前から楽しみにしていた分、気落ちが酷かった。
「おい、馬鹿女。お前一人なのか」
酷かったが。
「……ベネディクト」
後ろからかけられた、皮肉交じりの台詞に涙は引っ込んだ。
渦中の人物であるヴァイオレット・エヴァーガーデンは時を同じくしてある男と対立するように向かい合っていた。人混みを避けて、演習場を囲む木々の影に佇む二人はまるで恋人同士だ。会場から完全に姿が見えない訳ではないので、遠目からは逢瀬を交わしているように見えるだろう。
「お久しぶりです」
長い黒髪。翠の瞳。
「……」
男は鬱陶しそうにヴァイオレットを、その翠の瞳で睨む。
人の流れに何度も見失いそうになりながら、ようやく腕を掴み引き止めた時から彼は不機嫌だった。時間はその時に少し戻る。
「お待ちください」
ヴァイオレットが掴んだ腕を、乱暴に解きながら男は振り返った。彼女の成長した姿が自分が見ていた時とあまりにもかけ離れていたせいか、男の反応は少し遅れた。相手が誰かと判明すると、あからさまに舌打ちをしてヴァイオレットの肩を突き飛ばした。
「触るな」
彼はヴァイオレットが思い描いていた男とよく似ていたが違った。突き飛ばされても、体幹で受け止めびくりともしないヴァイオレットを気味悪そうに眺める。
「覚えて、いらっしゃらないかもしれませんが……」
「覚えてるよ。俺の仲間を滅茶苦茶に殺した殺人鬼を忘れるわけないだろ」
ギルベルトの兄、ディートフリート・ブーゲンビリアがそこに居た。
まっすぐに突き刺さる言葉にヴァイオレットは目を一度ゆっくりと瞬いた。
ディートフリート・ブーゲンビリアは、彼女がかつて出会ったエドワード・ジョーンズとはまた違うが、ヴァイオレットの過去を暴いて開いて見せるという点では至極似ていた。
「はい」
ヴァイオレットは、ただ、それを受け止めて返事をした。
「何してるんだお前……お前みたいなのは管理されてないと駄目だろ。主人はどうした」
ディートフリートは海軍の詰襟制服を着ていた。仕事絡みで此処を訪れたのだろうか。返事をすることが出来ないヴァイオレットに、ディートフリートは舌打ちして更に言う。
「……ギルベルトのことじゃない。いまは、あれの友人に拾われて使われてるんだろ。早くそこに帰れ。うろつくな」
犬の子を追い払う仕草をする。
「知ってらっしゃるんですか」
すらすらと話すヴァイオレットの様子はディートフリートにとって一体どのように映っているのだろう。彼が出会った時は言葉の話せぬ知能の低い化物だった。
「……ふざけるな」
美しい外見は、成長した姿は、更なる怯えを彼に産んでいるように見える。
「兄弟のことだ。それも不始末。当たり前だろう。あれは俺の弟なんだぞ。来い、お前が人混みにいると不安になる」
ディートフリートは苛つきを見せる。その怒りの感情のままヴァイオレットの腕を乱暴に掴んだ。ぎしり、と派手な音がして、驚いて一度手を放した。
腕を見てからヴァイオレットの顔を見る。二人共緊張していた。草原のど真ん中で出会った草食動物と肉食動物の如く、どちらかが先に動くか迷っている。
「武器は、持っていません。誰も殺しません。殺すなと、言われています。私も……命令でなくても、しません」
ヴァイオレットは両の手を開き、武装をしていないことを強調する。
「信じられるか。本当にそうなのか? お前、命令が欲しいだけの道具だろ。俺は手放したがお前、例えば命じたらそうするんじゃないのか。なあ。昔は俺の命令でそうしていただろう」
「しません」

ディートフリートはヴァイオレットの胸元に指先で作った銃を突きつけた。
爪が、ぐさりと谷間に突き刺さる。
男の大きな指先から与えられる生々しい感触に、自己防衛反応が出そうになる。普段の彼女なら即座に行動している。だが、動かなかった。
「自分を殺せ」
ヴァイオレットは、呼吸が一度停止した。
一秒、二秒、三秒、止まる呼吸。再開されて体に空気が満たされても、顔は青ざめていた。
目の前の男、敬愛する主の面影を抱かせる風貌の男から齎された言葉に、心音すら止まりそうになる。
それでも、ヴァイオレットは言う。
「しません。生きろと、命じられています」
精一杯の返事は、哀音が混じっていた。
「……そうかよ。惜しかった。これを思いついたの、ギルに渡した後だったんだよ……どうせあいつが死ぬなとか言ったんだろ。……本当に、惜しかった。あいつは甘い。お前なんてギルベルトに使われる内に死ねばよかったのに。おめおめとまだ生きやがって。俺は……お前が殺した部下の家族に、未だに会いに行って金を渡してる……」
ヴァイオレットの碧眼の視界がぐらついた。抜かれた指先には血こそついていなかったが言葉は暴力と同様に衝撃と痛みを与えた。
「わ、た、し……できることが」
「何も要らない!! お前からなんか!」
大きな声を出したせいか注目を浴びた。軍服の男が一般人の女を恫喝している、そんな風に見えてしまう。
「……お前、もう、帰れ。帰れよ」
「まだ、ご質問があります」
ディートフリートは深い深い溜息をついた。前髪をかきあげてヴァイオレットを本当に憎々しげに睨む。そして、一度は放した機械の腕を掴んだ。
「……だったら他の客におかしく見えないよう振るまえ。場所を移動する」
察したヴァイオレットは出来る限りディートフリートに寄り添った。周囲に居た客もただの痴話喧嘩だと思ってくれたことだろう。二人はしばらく無言で歩いた。
ディートフリートは罵詈雑言をヴァイオレットに浴びせた割には人混みの中の誘導は女性として扱う配慮のあるものだった。意図せず自動的にやっていることなのかは表情で計りかねた。海軍の制服を着ているのだ。そうした振る舞いは当たり前なのかもしれない。
「……」
大人の男に、まるで守られるように歩くこと。
軍服姿に皆が楽しげに笑う風景の中、手を引かれ歩いたことはヴァイオレットにとって初めての経験ではなかったが人生に置いて稀な経験だった。前とは全く状況が違った。追う相手も。見上げる視点の高さも、何もかも。
大きくなった元少女兵は自然とエメラルドのブローチに手が伸びる。
幼い頃の方が、彼女は無敵だったのかもしれない。成長した自動手記人形のヴァイオレットは不安に揺れている。
人が少なくなるとディートフリートはヴァイオレットの腕を、捨てるように放した。
「俺に何か用か。恨み言なら聞かないぞ」
「恨んでなど、いません」
ディートフリートは鼻で笑う。
「……どうだか。俺は多方面から賞賛と恨みを買ってる。そういう性格なんでな。こうして後で闇討ちされそうになることは偶にあるんだ」
「しません。貴方にそんなこと、しません……」
ヴァイオレットの返事に翠の瞳が何とも言えぬ歪みを持った。最初の軽蔑とはまた違う怒りがその瞳には込められていた。にじり寄るディートフリートに押されるようにヴァイオレットは数歩下がる。大樹の幹に背中を打ちつけ、それでも視線は彼から外さず真摯に見つめ返すと顔横に拳が飛んだ。
「……」
殴られこそしなかったが、木片が頬を切った。血を流したのは彼女だけでは無かった。ヴァイオレットは横目でディートフリートの拳から流れる血を確認する。
「覚えているか……幼いお前を殴ったり蹴ったりしたことがあったな」
「はい……」
「お前は殺意を感じない限り、ある程度の暴力は俺からは受け入れていた。お前と居ると俺は同じように化物になるんだよ……。お前が俺をそうさせるんだ」
「私が、そう、させる……」
「そうだ。お前が悪い。いまだってそうだ。お前と居ると、話すと、苛々する。心が休まることがない。お前がそうさせるんだ。お前は俺の仲間を殺した。あの時のことが何度も何度も夢に出る。でも俺はお前を糞ほど嫌ってはいるが、恨んではいない。いや、ただひたすらお前のことが嫌いで堪らないが、恨みという感情とは違うんだ。諦めに近い。お前という欠陥品が世界に存在することを許してやらないといけないと思ってる……どうしてだかわかるか?」
ディートフリートはもう片方の拳でまた樹を殴った。
ヴァイオレットは眼をそらさない。その碧い瞳であるがままに相手を見る。
その瞳があまりにも青く澄んでいるからか、晒されたような心地をディートフリートに与えてしまう。
「お前が殺した俺の仲間の一人もお前を犯そうとした。だから殺された。ぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶ巡り回ってる! 巡り回ってるからなんだよ……!」
だから恨んでいない、とディートフリートは言う。
「私が、したことも……貴方が、されたことも?」
「そうだ。誰も教えてくれなかったか?」
ヴァイオレットは首を小さく振る。
「いいえ、教えて貰いました」
ホッジンズの予言がいま正に的中し、ヴァイオレットの身に降りかかっている。
『君はこれからたくさんのことを学ぶよ。そしたらきっと、自分がしてきたこと、俺が放置したと言ったこと。それが何なのかわかる時が来る』
『そして初めて、たくさん火傷をしてることに気付くんだ』
『まだ足元に火があるのを知る。油を注ぐ人が居ることを知る。知らないほうが楽に生きられるかもしれない。時に泣いてしまうこともあるだろう』
その瞳が永遠に閉じてしまうその時まで、我が身が燃えていることを知らない。
そうなる運命の化物だった。だが化物は、道具は、ヴァイオレットは。
いま、人として生きている。
青年の死を故郷に持ち帰り涙した時から、いや、もっと前から。
自分が火に巻かれ焦げていく匂いを嗅いでも、それでも、生きる方を選んだ。
「だから、お前が俺を恨んでいたとしても俺は言う。そんなの知ったことか、と」
人として生きる方を選ぶ、理由があった。
ただ、それのみが化物の少女の人生で光り輝く何かだったのだ。
「違います、違うんです…………お引き止めして申し訳ありません。私は、ただ……少佐のことを……お聞きしたくて」
ディートフリートはゆっくりと拳を放した。白手袋には血が滲んでいる。
「お前のせいで、滅茶苦茶になったあいつがなんだよ」
「どう、すれば」
「はあ?」
ヴァイオレット・エヴァーガーデンは、ディートフリート・ブーゲンビリアに尋ねる。
「道具、なのに守れませんでした。でも、生きろと言われ生きています。他に、何か、出来ることが……あったら、教えて欲しいのです。生きていて、いいのでしょうか。感情が、増えてしまいます。人と、関われば、関わるだけ、感情が。私は、少佐の道具なのに……でも、生きろと、言われ……私は、少佐を……」
かつては飼い主と化物、使い手と道具だった二人。
何もかも関係が変わってしまったというのに。
「知るかよ!! 何で俺に聞く!」
下僕は元の主人に教えを乞う。
「……貴方の、道具、だったから」
孤島で拾った化物が、いまは成長し物を語り、そして不安げに揺れている。
「道具なら意思を持つな!」
不安げに揺れて、助けを求めている。
「貴方が、私の、主人……だった、から」
その台詞に、ディートフリートは虚を突かれた。
――主だなんて、思っていたのかよ。
ヴァイオレットの碧の瞳は、美しく澄んでいる。それ故に過去に自分がさせたことをディートフリートに鏡のように思い出させる。
「……捨てた道具のことなんて知るか! お前は化物で、弟の人生をぶち壊した災厄だ!」
誰かに与えた事柄は、時を経てその者に遠回しに返ってくる。
「ディートフリート様、なら、私を、どうして……少佐に渡したのですか」
傷つけたことも、優しさも、遠回しに、帰ってくるのだ。
此方を射抜くような視線。すがっている、けれどそれを言えない視線。
ディートフリートと最期に別れる時に見せた瞳と同じだ。
その視線に刺されて、孤島から持ち帰り、唯一家族の中で交流がある弟に預けた。
何故、ギルベルトに預けたのか。
ヴァイオレットの言う通りだった。役に立つ道具だったが、ディートフリートは自分でもヴァイオレットを持て余していた。弟に託して彼がちゃんと使える確証があったとは思えない。殺せずとも、人売りにくれてやる選択肢も頭にあったはずだ。
ギルベルトはディートフリートに押し付けられたと感じていた。
ディートフリートは何を思い、ギルベルトにヴァイオレットを託したのか。
本当にギルベルトしか相手が居なかったのか?
他の海軍将校は?
選択肢は、その時、他にもあったはずだ。
だが、彼は家族に託した。
「お前に人間の感情がわかるのかよ」
ディートフリートは手を伸ばして、ヴァイオレットの胸ぐらを掴んだ。
殴りたいのか。殺したいのか。それとも。
「わ、か」
「わかるなら死ねよ。俺の怒りや悲しみを受け止めろ。でもお前、俺が死ねと言っても死なないんだろう」
「……はい」
「俺も死なない。お前が何を悩んでるのか、理解してやりたくもない。俺はお前よりもっとひどいことを人生でしてきてる。だがそれがどうした。俺は生きる。死んだらそれまでだ。俺にだって悲しいことや辛いことはある。こりゃあ死んじまったほうがいいと思って、現にそうしようかと思う時もある。自分だけ辛いような顔しやがって、皆辛いんだよ。お前に殺されたあいつらも俺が関わらなきゃ死んでなかった。それは俺のせいかもしれん。俺のせいかもしれん。俺は指揮官だったんだ。あいつらを守って導けなかった。だが、な。化物。お前、少しでもそれを後悔しているなら、どんな理由であっても、死ねないなら。誰かに殺されるまで、それかお前が寿命でくたばるまで生きろ。死ぬより、なあ」
殴りたいのか、殺したいのか、それとも。
「生きるほうが辛い。生きるほうが辛い」
それとも。
「生きるほうが辛いんだ。でも、全部呑み込んでそれでも生きろ。出来ない奴から死んでくだけだ。自分で死ねねえなら、お前の罪も何もかも、誰のせいにもしないで生きろ。生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、生きて」
胸ぐらを掴んでいた手をぱっと放した。
「そして、死ね」
ヴァイオレットは、ギルベルトに送る視線とはまた違う、だが確かに主を見つめる目で見上げる。
「ディートフリート様。少佐は本当に……死んでしまったのですか」
「何て言って、欲しいんだ」
その言葉に、ヴァイオレットは息をふっとのむ。きらりと光る物を、空の向こう側で見た。
「…………他の方みたいに、そうだと、言わないんですね。いま、確信しました。もし少佐が死んでいるなら、きっと、もうその時点で貴方は、私を、どうしたって殺しています」
ヴァイオレットの見上げる視界。
ディートフリートの頭上から、青い空から何かが降ってくる。雪のように、花のように。
「生きて、いらっしゃるんですね」
飛行手紙が降っているのだ。一陣の風が吹いて二人の間をごうと吹きすさぶ。
手紙が吹雪の如く流れてきた。青い空を切り裂く黄色の飛行機が飛んでいる。幾人もの思いが乗せられた手紙を撒き散らし地上の人へ届けている。
この中から選べと。落ちてきて、拾った一通の手紙が貴方の運命を応援するのだと。
「ヴァイオレット!」
奪われた視界の中でヴァイオレットは名前を呼んだ誰かに無理やり体を荷物のように担がれた。ディートフリートが遠く、どんどん遠くなる。
彼の名を囁いてみたがもう届かない。
彼がくるりと踵を返すのが最後に見えた。一度もこちらに視線はくれなかった。
ヴァイオレットは必死に自分を攫う人。走る彼に声をかける。
「ホッジンズ、社長」
「頭低くしてて!」
「大丈夫です。ホッジンズ社長」
「大丈夫じゃない! 何で、あんなやばい人といるんだ!」
ヴァイオレットは先程確認した光る対象の場所をもう一度確認する。
もう、そこには何も見えなかった。
「本当に大丈夫です。私が、高台から彼の部下に狙撃銃で狙われていたのは気付いていました」
「狙撃って……!」
「護衛が一緒にいませんでしたから、近付いた時点でその危険性は考慮していたんです……あの方は、いつも護衛を連れて歩いていましたから……居ない時点でわかっていました。けれどあれは牽制でしていただけです。彼は合図を出す気がありませんでした。ホッジンズ社長、お仕事はよろしいんですか」
この冷静さは普段なら頼りがいがあるが、今回はそうは言っていられなかった。
ホッジンズは怒りと焦り、安堵が混ざった声音で返す。
「カトレアが泣くからと思って、早く切り上げたんだよ……そしたら、君が軍服の人を追いかけていったって聞いて、もう肝が冷えた……ギルベルトの兄さんになんてもう絶対に会うな、ヴァイオレットちゃん。あの人は、ギルベルトと血はつながっていても、まったく別の人なんだ。元主でも駄目だ。怖い人なんだよ。君を、嫌ってる。俺がうかつだった……今度から、お祭りといえどこういうのには参加させない。君が軍に戻されるかと思った……今日はもう帰らせるよ。いいね」
「はい」
「何か言われた? 大丈夫?」
ヴァイオレットはすぐに答えなかった。空に手を伸ばしていた。
「……」
ホッジンズに担がれたまま、誰かからの手紙を一通受け取る。
「ねえ、何か変なこと言われたのか? ヴァイオレットちゃん?」
誰かが誰かへ向けた、思いを受け取る。
「いいえ、いいえ……何も……ただ、頂いただけです」
生きて。
「何を?」
誰のせいにもせず。
生きて。
生きて。
生きて。
「激励を」
そして、死ね。
舞い散る手紙の中でディートフリートが歩いていた。
人々が飛行手紙に夢中になっている演習場の中心から足を遠のかせ関係者以外立ち入り禁止の管制塔へと入る。同じ海軍の制服の者達、それに陸軍の制服の者達が目礼をする。
「くだらんことをしていたら、うちの部下の曲芸飛行を見そこねた」
その中の一人の横に立ち、声をかけた。
「まだ飛んでる」
話しかけられた男は、ギイ、と機械の腕を鳴らしながら空を指差す。
「数年ぶりだな」
ディートフリートが知っていた頃の姿とは違う男がいた。片目が眼帯で覆われ、裂傷が見え隠れしている。宵闇の髪。エメラルドグリーンの瞳は宝石の如く。
憂いを含んだ横顔は冷たさを孕んでいる。
長身な体躯を包むのは軍事国家として名を馳せる海寄りの国、ライデンシャフトリヒの紫黒の軍服。一兵士が纏うものではない。金章付きの外套が彼の階級の高さを知らしめていた。
ギルベルトがディートフリートに掴まれた肩を振り払う。
「……つれないな。先程、お前の道具に会ったぞ」
二人にとって、道具とは何を指し示すかは決まっていた。
「……」
「嘘じゃない。俺を追いかけてきた。お前と勘違いしたわけじゃなさそうだが。お前気を付けろよ。死んだことにしてるんだろ。何でまた面倒なやり方をするのか……」
「兄さん、ヴァイオレットに」
「何も話しちゃいない」
ディートフリートは嘘は言っていなかった。
「お前がいなくなって途方にくれてるみたいだから。元主として言ってやっただけだ。生きるだけ生きて死ねって」
あの時、否定をしなかったせいでヴァイオレット・エヴァーガーデンは抱いていた希望を確信に変えてしまった。
「……」
それを弟に言うつもりはない。
「それがお前の望みなんだろ。あれは、たぶんそうではないが。気が付いたら、誰かに連れられていた。目立つ赤髪をしていたからお前の士官学校時代からの同期だろ。俺に殺されるとでも思ったんだろうな。ははっ殺せるか。俺が殺されるならまだしも……なあ、ギル。お前まさかあの化物のこと好きだとか言わないよな。随分良い女には育っていたが、中身を知ってるだろ。やめておけよ」
「……関係ない」
「関係ある。お前が大事だ。俺の弟だ」
「私とヴァイオレットのことだ。他の誰にも、関係ない。その大事な弟に、なにもかも押し付けたのは兄さんだろ。残された私が、何を……」
ギルベルトはエメラルドの瞳を歪ませた。
空を見上げるのが眼に眩しくて痛かった。だが、眼を瞑りはしなかった。
「何を一生かけて、守ろうと私の勝手だ。その為の地位を築いている。いま、私が生きているのは、陸軍で更なる高みを目指しているのは、兄さんの尻拭いではない。ブーゲンビリアの家の為でもない。あの子の為だ。何かしようとしたら、私のすべてを持ってして叩き潰す。その為の武器だ。相手が、兄さんであってもそれは変わらない」
久しぶりに会った弟の変わりぶりに、ディートフリートはギルベルトが空を眩しく眺めるように見つめた。
「……お前、もう小さくないんだなぁ」
ディートフリートは拳を固く握ってギルベルトの肩を殴ろうとした。
それをギルベルトが受け止めた。そのまま、手の平で包んで握る。ディートフリートは手の痛みをこらえて嗤った。
まるで小さい頃に、手を繋いでいた二人だ。
「なあ、俺はお前にとってよくない兄かもしれないけどよ。愛してるからな」
兄弟は内緒話をする。他の誰にも聞かれない小さな声で。
「知ってる」
ブーゲンビリアの家ではいつもそうして、話していた。
怒られないよう、二人でただひっそりと。
「……本当に、わかってくれよな。これでも、精一杯、愛してるんだ。愛してるよギルベルト……俺、どうしてかな。こういうの、本当に好きな奴にはうまく伝わらないんだよ」
「知ってるよ、兄さん」
夜の帳が下りた中、航空展覧会を後にした人達は月明かりや部屋のランプの灯りを頼りに見知らぬ誰かが自分に贈ってくれた励ましの言葉を読んでいた。
自分の書いた手紙は誰かを励ませているだろうか?
思いを馳せながら今日という日を噛みしめる。
その日は佳き日だったかもしれない。そうではなかったかもしれない。
どちらにせよ、無条件に与えられる優しさは夜長の寂しさを、明日への不安を減らして少しばかりの希望を与えてくれる。
一人、エヴァーガーデン邸に帰されたヴァイオレットは一通だけ持って帰った飛行手紙の封筒を窓辺に佇みながら開いてみた。
「はい」
そこには、子どもが書いたと思われる字で「げんきをだして」とだけ書かれてあった。
ぜひこの機会に『ヴァイオレット』を読んでみてくださいね!
KAエスマ文庫『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズ刊行10周年記念企画特設ページ
https://www.kyotoanimation.co.jp/books/violet/special/10th/