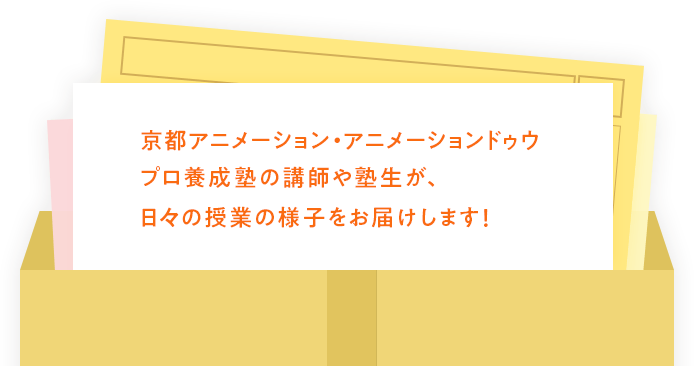2023.12.29
卒業制作に取り組み始めて約1ヶ月ほど経ちました。
現在レイアウトを終え原画作業に入っています。
私の卒業制作ではアクションをテーマにし、それぞれのキャラクターが生き生きと動き、見応えのあるアニメーションになるよう日々取り組んでいます。
ですが特に原画作業をしている中でイメージした動きを描き起こすことはとても難しく自分の引き出しの少なさに悩まされます。
今まで私は自分の固定観念だけで動きを描いてしまう癖がありました。結果リアリティのない動きになってしまうことが多々あり、講師の方に指摘を受け自分の癖に気がつきました。
癖を自覚し卒業制作に入ってからは実際に自分で動いて撮影し確認することを大切にしています。
今まで自分では想像もしてこなかった予備動作や体のひねり、重心移動など多くの発見があります。
その発見をどうキャラクターの芝居に落とし込むかの試行錯誤がとても楽しく、同時に難しさも感じています。
画力不足や知識不足で理想通りに進まないこともありますが、今の自分に出来ることを地道に積み重ね、最後納得のいく卒業制作になるよう頑張りたいです。
なによりこの環境でアニメーションを学べることを楽しみながら、これからも精一杯卒業制作に取り組んでいきます。