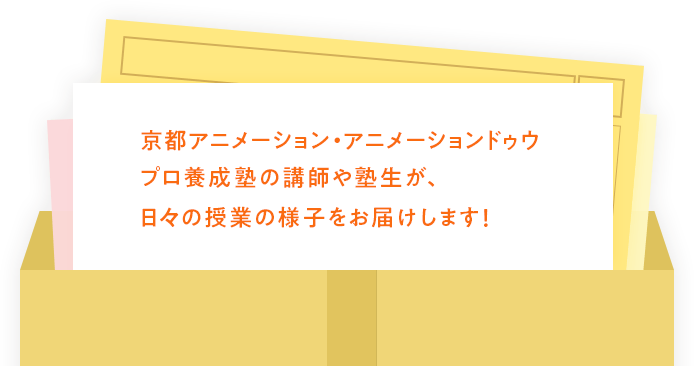2023.05.26
プロ養成塾に入塾してから、一ヶ月以上が経ちました。時間が過ぎるのがとても早く感じます。
目標だった養成塾に入塾したことに未だ実感が湧かないのですが、同じ志で集まった仲間達がいて、日々アニメーションについて新しい知識が増えていくのが本当に楽しいです。
この一ヶ月様々な授業を受けてきた中で、今一番悩まされているのは「飛び越える」という課題です。人物を崖から崖へ飛び越えさせる動きの表現です。
崖と崖の間には距離があるため、まずは助走を描くのですが、私は大きくジャンプさせることに気をとられてしまい、本来なら助走の勢いで重心が前に向かって飛ぶはずが、上へ高くジャンプさせていました。
そのことを講師に指摘されるまでまったく気づかなかったことに、衝撃と自分の観察力不足を痛感しました。
塾の課題に取り組むようになって改めて、「観察する」ことと、「自分で動いてみる」ことの大切さを実感しています。
想像だけで描かず、実際に自分で動いてみて、よく観察することが私の今の課題です。
少しの時間も無駄にせず、日常の物事を観察し、それらを絵に描き起こすにはどうすればいいのかを常に考えるようにしていきたいです。
同じ「飛び越える」という動きでも、運動の得意な人と苦手な人の動きの違い、馬、猫、鳥、生き物によっても違いがあり、キャラクターやシチュエーションによっても様々な動き方があり、これから考えることはまだまだ沢山あります。
私自身も、助走を忘れずに、前のめりに大きく飛躍していきたいです。
これからの一年間を充実したものにするためにも、1分1秒を大切に学んでいきます。