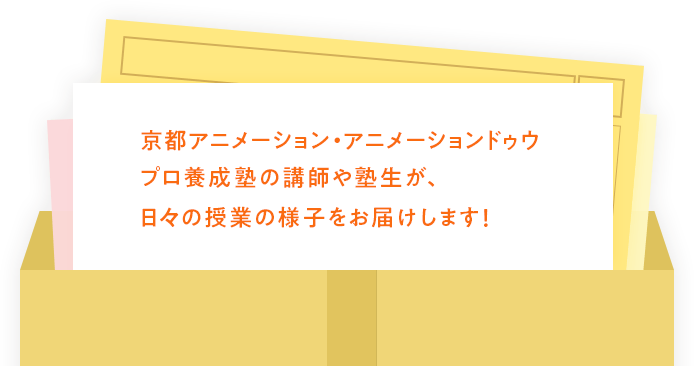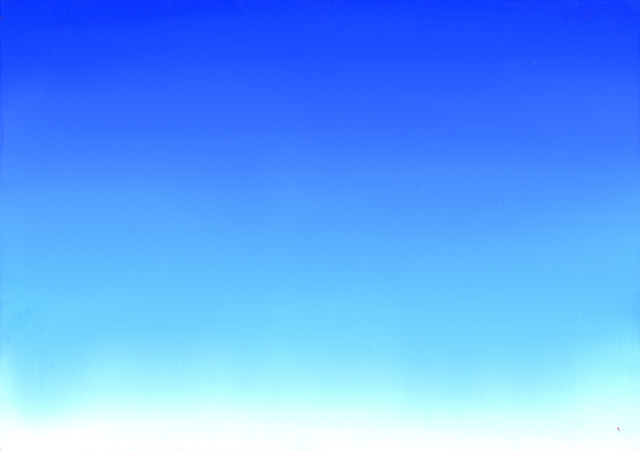2020.08.28
美術・背景科講師の篠原です。
授業の中で絵をチェックしているとき、小手先の技術面の他に、そのものの構造について気になった箇所を指摘することがあります。
実在するものが違和感のあるように描かれていると、それが気になり上手い下手以前の問題になってしまいます。
構図や配色、線画の魅力なども大事ですが、“あるものをそれらしく描く”ということは絵に説得力を持たせる上で非常に重要であり、また想像以上に難しいことだと感じています。
普段よく目にしているものでも、いざ描いてみるとどこか違う、上手く描けない……というのは多くの人が経験したことがあるのではないでしょうか。
その度、あぁ知らなかったのだと気付いて一つずつでも覚えていく事、意識して目を向けていく事、そういった事が絵の上達に繋がっていく一つの方法なのかなと思います。
「食べているとき、寝ているとき以外は仕事をしているのと同じである。」と、入社したての頃に先輩から教わりました。捉えようによっては極端な話かもしれませんが、プロとしてやっていくならそれぐらいの意識を持って過ごすのが丁度良いと感じています。
塾生の今だからこそできる事を絞り出し、益々の上達に繋げていって欲しいと思います。