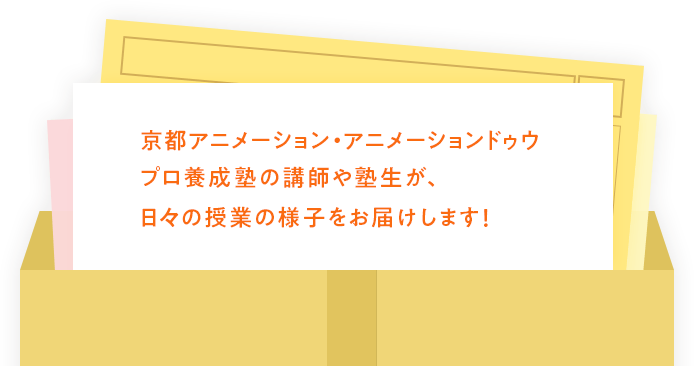【京都アニメーション アニメーター科 第29期前期生】
現在取り組んでいる「動き」の課題について記します。
私が動きの課題で講師から頂いた最初の評価が、「出来の悪いワイヤーアクションのようだ」でした。とてもショックでした。始めは講師が教えてくださる事の内容がよく理解できず、その事が気になり夜も眠れないほどでした。しかし言われたことを噛み締めよく考えていく事により、段々と課題に生かす事ができるようになっていました。
そして最近になり、私は始めに描いた課題を見て大きな成長を実感しました。確かに動きに力強さもない出来の悪いワイヤーアクションのようだと感じるほどに。
絵に限りませんが、常に考える事。ただ数をこなせば良いわけではなく、何故理想の動きにならないのか、重心か、タイミングか、手か、足か、画力か、はたまた根本的な考え方が違うのか。描いて見て考えて描いて考えて見て描き続ける事こそが大きな成長に繋がるのだと感じました。
しかしそればかりでもただ疲れるので楽しく自信を持つ事も忘れずに描き続けたいと思います。
【京都アニメーション アニメーター科 第29期前期生】
現在『立ち止まる→走り出す』の作画課題に取り組んでいます。キャラクターが画面外から勢いよく走り込み途中で停止して、その後再び画面外へと走り抜けていく一連の動きを描いています。私は難航しているこの課題ですが、講師の方の力を借りて何度も修正していくうちに、アニメを描くことの醍醐味が見えてきたと感じ始めました。
それは当然の動きを当然に見えるように描くことの難しさ、という話でもあります。私たちが日常生活で無意識に、あるいは意識的に行っている動作には実はたくさんの決まり事があり、キャラクターの動きにはそれらが適切に落とし込まれている必要があります。だからといって必要と思われる要素のみに絞った絵で揃えても記号的で、求めている自然さからは遠くかけ離れることになり、自然且つ華のある良い動きを描こうと思ったら、その運動の要点を掴んだうえで私自身の実感を絵に乗せることができなければならず、講師の方からはよく自分の描いた動きの感触や印象を尋ねられることになりました。そして、それを言葉にするのが難しいと感じる度、見てもらうことで感覚を共有できるだけのものを作れればいいのに、ともどかしさを感じてしまいます。
しかし、この難しさがそのまま描くことの楽しみといえるのかもしれない、とある時ふと思い至りました。思うようにならないことばかりだからこそ、思いもよらぬ興味深い意見、素晴らしい提案に出会えることもあります。試行錯誤しながら出来上がったものはまだいまいちでも、良い変化を望んで向き合っている時間は確かに楽しいものです。
学んだアニメのセオリー、そして楽しみを大事に、今後も自分の課題と共に良い時間を過ごせるよう努めていきたいと思います。