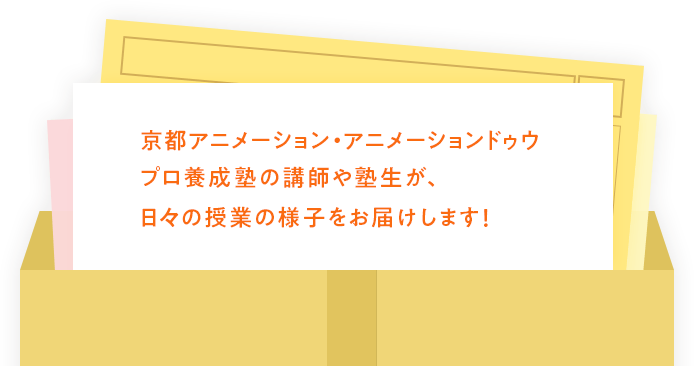2020.07.08
【アニメーションドゥウ アニメーター科 第29期前期生】
塾が始業し早3か月が経ちました。4月中旬から5月末まで続いた自宅学習期間も終わり、 やっと元通りの通塾生活が戻ってきました。3か月も課題をこなし続けていると、そろそろ自分の課題がハッキリしてくる頃です。
現在私は、クリンナップから中割りに移行した段階にあります。まず、大まかに言いますとクリンナップとは原画を一本線の滑らかな絵に仕上げる作業です。新人アニメーターが最初に取り掛かる作業行程であり、これができないと始まらないとのことでした。そしてこの次の段階が中割りになります。原画と原画の間に絵を足し、対象物の動きを滑らかにする仕事です。
次の段階と記しましたが、作業量が増えたとしてもクリンナップの心得を忘れてはなりません。講師陣からは度々「クリンナップはなぞるだけの作業ではない」「対象物の形を捉え、(表情は特に)ニュアンスを拾うのが大事」「柔らかい線を」など指摘を受けます。頭では分かっていても目先の線にしか注意が向かず、なかなか思う線が引けませんでした。
そんな時、塾が再開して間もない日の授業で、クリンナップの添削をしていただいた時の事でした。講師の先生に目の前で私のクリンナップを描き直していただき、驚いたのです。Youtubeに、画質設定のボタンがあると思います。144pは最も粗い画質設定ですが、これが私のクリンナップ品質と考えてください。その上から講師の先生が描かれた途端、最上画質の1080pになってしまったのです。これが画面でなく、紙面上で行われたものだった(そして、こんな場面を目の当たりにするのは人生で初めての経験だった)ので、とても驚きました。それに、作業風景を間近で見ることによって、度々指摘をいただいていた事がはっきりと理解できたのです。それ以降私のクリンナップはガラっと変わり、日々自分の思うような線に近づきつつあると感じております。
数を描くのは勿論大切です。ただ、この経験から「見る」ことも同じかそれ以上大切だと実感しました。
【アニメーションドゥウ アニメーター科 第29期前期生】
現在取り組んでいる作画課題「飛び越える」で得た学びをお話します。
アニメーションは人物、感情、空間、物、風、光も影も言ってしまえば全てが嘘の作り物です。
ではなぜ作品を観ていて登場人物に深く共感したり、目が腫れるまで涙を流したりドキドキするほどの勇気が溢れてきたりするのでしょうか。
まず、アニメーションの作画ではキャラクターが動いているように見せる為に実際の人間の動作より誇張させたポーズでキャラクターを描けねばなりません。
しかしその一方で、一連の動きとして嘘にならない現実味のあるもの、リアリティーも求められます。
誇張とリアリティー、双方の兼ね合いの末にキャラクターは説得力のある動きになり、説得力を持った存在になるのだということを学びました。
そのように「生きている」という説得力を作品の中のキャラクターひとりひとりがしっかり持っているからこそ、共感、感動、興奮ができるのかもしれません。
そしてその説得力のある動きを作り出すことがアニメーターだからこそできることのひとつなのだと思います。
このような気付きや学びのひとつひとつを大事に、焦らず零さず一歩ずつ進んでゆきます。