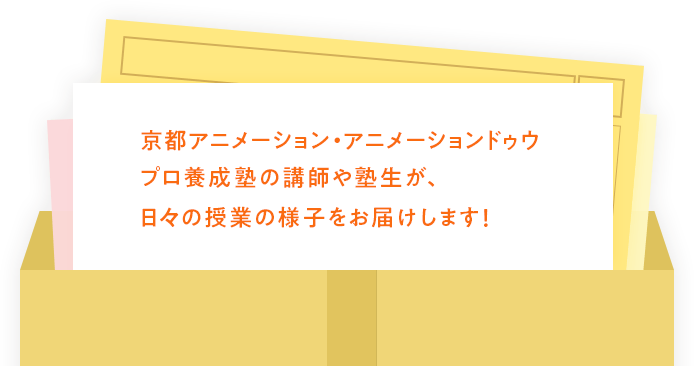2021.10.29
【アニメーションドゥウ アニメーター科 第30期生】
前期を振り返ると、半年間に得た知識や経験から見えるものが増えた分、自分には足りないものが溢れかえっているとわかります。とはいえ、あれもこれもというわけにはいかないので、落ち着いて「今目の前の課題から着実に行くしかないぞ」と自分自身に言い聞かせる日々です。
そんな中、動きの課題に取り組む中で今更ながらに気付かされたことがありました。
ラフの段階で迷い線が何重にも重なった動きを描き、動かしてみるとその時はそれっぽくはなってくれるのですが、いざ線を絞って清書すると、ラフのときとは違いイメージとは異なる動きになってしまってしまう。加えて、頭身がバラバラ になってしまうということが多々ありました。
これはただ画力の問題だと自分自身思い込んでいたのですが、講師の方から「主体性が足りていないのが原因ではないか」といったお言葉をいただいた時に、 ハッとしました。今の自分にはここまでしかできないと目標の手前の低いラインに決めつけ、元の絵に合わせようという責任感が足りていなかったと思います。 一生懸命に取り組んでいたとしても、最初から目指すところが手前ならば遠回りしているのと同じことだと感じ、反省しました。結局最後は清書をしないといけないのだから、最初からそのつもりで線を引いていくべきでした。
後期では前期の反省を生かし、もっと先を見て、ここまで描くぞという気持ちをより一層強く持ちたいと思います。次は前より良いものを、という思いで日々更新していけるように常に鍛錬を欠かさず、時間を大切に過ごしていきます。